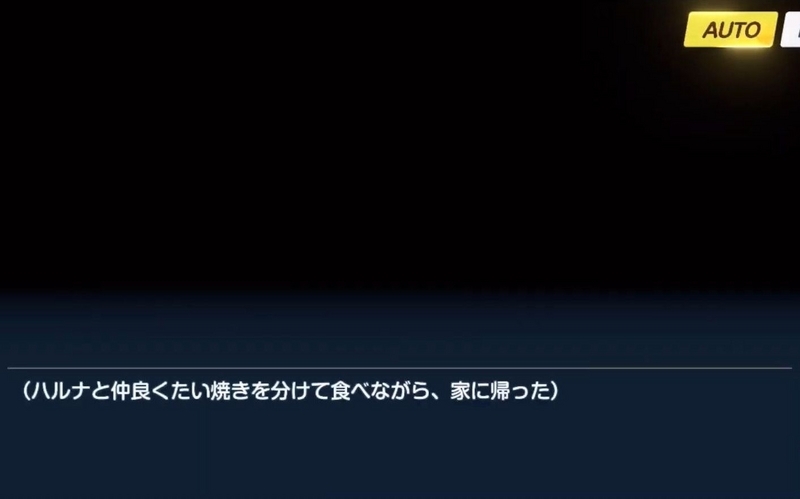美食を追い求めていた富裕階層の少女が好きな人と食べることこそ最高の食事であると悟る話。
黒舘ハルナは美食を求めて溺れてきたが最近飽食の余り高級なレストランや料理店に興味を失い始める。
それ故、高級な素材を手に入れ敢えて安い簡易食品を作るといった行為などをするようになっていく。
そんなハルナが最終的に気付いたのは、好きな人と一緒に食べる食事が一番美味しいという境地であった。
逆孤独のグルメであり、何を食べても一人では味気なく、先生と食べることに喜びがあったのである。
ついにハルナは先生に食べさせあいっこを求めだし余韻として先生と過ごすことも食事に含めるようになる。
バレンタインではチョコの甘さは想いの深さの比喩である言い出し、超絶甘いチョコを先生に作ってあげる。
だがその甘さ=先生に対する気持ちということに気付いたハルナは自分の好意を自覚し逃げ出すことになる。
黒舘ハルナのキャラクター表現とフラグ生成過程


黒舘ハルナは富裕階層に属し美味しい物を食べることを追究するセレブな御令嬢であった。美食のためには高級食材を手に入れて自ら腕を振るうこともしばしばあった。だが、飽食のあまり、最近では食べることに関して色々と考えるようになってきてしまったとのこと。どんなに美味しいものを食べたとしても味覚の情報を食べているだけでどこか満たされない日々が続く。そんなハルナを変えることになるのが、先生の存在であった。気の置けない親しい人たちと食べる楽しい食事こそがハルナの求めるものであったと気付き始めるのである。最早薄ぼんやりとした記憶ですが銀英伝でも廉価なファストフードを仲間たちと美味しそうに食べる場面があり、それが非常に巧みな描写のように感じられたことが脳裡にこびりついているが、まさにそれ。ハルナはいくら高級なレストランでも一人きりで食べてはつまらないと感じていくようになるのであった。逆孤独のグルメ。ハルナは料理を特に美味しいと感じられるようになるのは、先生と一緒に食べる時だと気付くようになる。飽食の空虚さを抱えるハルナは先生と屋台の鯛焼きをあ~んした時に特別な味わいを覚えるのであった。


正月版ではさらに先生と食べる事の幸せが強調されていく。正月屋台のB級グルメであっても振袖を身に纏い人が賑わう中で先生と腕組をしながら食べる料理はハルナにとって味わい深いものとなる。さらに競りに参加し高級な鯛を手に入れ、行きつけの高級料理人に食事を提供してもらったとしても、料理の味よりも先生をもてなして喜んでもらった時の感情の方が優先されるものになっていく。そのトドメとなるのがおせち料理の食べさせ合いっこ。ハルナはおせちを用意し先生を誘うのだが、そこでお互いにおせちを食べさせ合いたいとねだるようになる。先生にあ~んするだけではなく、自分も餌付けのように料理を口に運んでくれるよう求めるのである。こうしてハルナは先生と食べさせ合いっこをすることを最高の美食だと感じるようになっていった。さらに食事は食べるだけではなく、その余韻も含めて食事なのだ。ハルナは冷たくなってしまった手を温め合いたいと先生に寄り添い、手を取って街歩きを楽しむのであった。


バレンタインではチョコの甘さは愛情の深さの比喩だと称しておもくそ甘い抹茶チョコを作ろうとしてくる。甘さが愛情深さであり、その甘味を最大級にしたいということは、それ即ち先生好き好き大好きであると言っていると同義なのであるが、チョコづくりに拘るハルナはそのことに気付かない。ハルナがそのことに気付いたのは先生にチョコを振る舞い、とっても甘いと言われた時であった。ここでハルナは婉曲的にとはいえ、先生に対する好意が駄々洩れであったことに気付く。普段から先生ベッタリになっていたハルナであったが、それには美食を探究するためという口実があった。だがここではその包まれていたオブラートが破れ自分の先生に対する好意に直面することになったのだ。初めての感情に戸惑うハルナは思わず先生の下から逃げ出してしまうのであった。